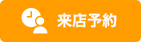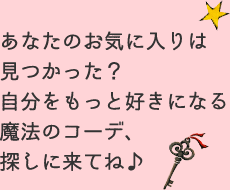Showa period 移り変わる昭和時代のスタイル
昭和はこんな時代
日本で最初の元号「大化」から数えて230番目(南北朝時代の北朝の元号を入れると246番目)の「昭和」は、史上最も長い62年(と2週間)続いた元号で、西暦でいえば20世紀(1926~1989年)の半分以上を占めています。ひとつの元号が60年を超えた例は世界でも珍しく昭和を含めてふたつしかありません(清朝の「康熙(こうき)」)。
昭和といえば日本では未曽有の好景気に沸くバブルのイメージが強いかもしれませんが、実は内閣府の景気動向指数で見るとほんの一部、昭和61年~平成3年(1986〜1991年)の間です。
むしろ世界的に見ると20世紀は「戦争の世紀」と呼ばれています。
大正時代には第一次世界大戦の勝ち組として戦後の好景気に沸きましたが、それも長くは続きません。戦後恐慌、さらに関東大震災などが重なり、大正の終わりから昭和元年あたりは散々なものでした。
その後再び第二次世界大戦(1939~1945年)が勃発し、今度は敗戦国として悲惨な戦後不況に陥ります。復活を遂げるのは「高度経済成長期」と呼ばれる昭和30~40年代になってからのことで、その間の経済成長率は世界1位となっています。
和洋折衷の昭和モダン
昭和という時代は第二次世界大戦の「戦前」と「戦後」で明確に分けられます。
戦前に花開いた和洋折衷の文化は「昭和モダン」と呼ばれることがあります。
戦前の日本は大正時代からの経済の発展と、欧米企業の盛んな進出によって、華やかな西洋の芸術や娯楽、ファッションが再び時代を彩ります。
既に政府主導の欧化政策からは40年以上の月日が流れていたため、文化的な摩擦はほとんどなく西洋文明は人々に受け入れられ、いよいよ大衆文化が花開くことになります。
芸術のジャンルでは、既に浸透していた日本的な自然主義の要素を含むアール・ヌーボー(Art nouveau)に加えて、より近代的に洗練された(量産に向いている)幾何学模様のアール・デコ(Arts décoratifs/装飾美術)の影響も見られるようになります。
既に大正時代に発行されていた文芸誌『白樺』が、ピカソをはじめとしたキュビスムやフォーヴィスム、シュルレアリスムの作品を紹介すると、自由な表現が可能になった時代の風潮に呼応するように前衛的な作品も好まれるようになりました。
またこの時代は発明王エジソンによる特許侵害の訴訟を逃れるために独立系の映画会社がハリウッドに集結。やがてハリウッドでの映画産業が盛んになり、海外の映画が日本でも上映されるようになります。
喜劇王チャーリー・チャップリンも昭和7年に初来日しました。
映画の大画面の中に映る華やかな西洋文化は日本の人々を大いに刺激し、本格的な大量生産・大量消費社会が訪れます。
少し後の話ですがジェームス・ディーン『理由なき反抗(昭和30年)』が日本でもヒットしてジーンズが売れたように、インターネットのない時代に映画は大衆文化に大きな影響を及ぼすメディアでした。
それまで音のなかったサイレント映画に音がついて(トーキー映画)世界中に普及していったのも戦前のこの時代です。世界初のトーキー映画が上映されたのが1927年(『ジャズ・シンガー』)で、日本初のトーキー映画は昭和6年の(『マダムと女房』)ですから、たった3年で世界標準に追いついた日本の技術の進歩も目覚ましいものでした。
大正15年に全国放送が開始されたラジオの受信機も、大量生産の効果で低価格化が進み一気に普及が進みました。ラジオから流れてくるフランスのシャンソンやアメリカのジャズの調べは日本の暮らしに西洋の流行が馴染んでいく大正浪漫の夢の続きのB.G.M.のようでした。
ちなみに高柳健次郎博士が世界で初めてテレビの送受信(カタカナの「イ」をブラウン管に映した)に成功したのもこの頃です。
復興から生まれた昭和レトロ
大正浪漫から昭和モダンまで、西洋文明を積極的に採り入れて近代社会へと成長した日本でしたが、戦争の足音が迫る中で人々の暮らしは慎ましやかになっていきます。
質素であることが美徳とされ、西洋風の華やかなファッションは身を潜めていくこととなります。男性は木綿の着物か襟なしシャツにズボン、女性も絣などの地味な木綿の着物に半幅帯を締めるのが普通になりました。
戦争中はもちろん更に倹約が強制され、家庭にあった金属は全て武器を作るために接収。各家庭で可愛がられていた犬や猫、馬なども毛皮や食用として供出要請されました。
華やかだった大量生産・大量消費の近代社会の暮らしは泡沫の夢のように消えたのです。
人類史上最大の死傷者数を出した悲惨な戦争(第二次世界大戦)が終わると、敗戦国の日本は7年にもわたって日本史上初めて他の国(アメリカ)に占領されます。
しかし敗戦の悲しみよりも悲惨な戦争が終わったことに人々は安堵し、華やかだった古き善き大正浪漫への憧れを胸に戦後の復興へと進みだします。
物のない時代に贅沢はできないけれど、少しでも暮らしが明るくなるように人々は努めました。華やかな模様のアデリアのコップでソーダ水を飲み、日用品はカラフルで安価なプラスチック製のものが使われました。
着る服も既製品を買わずに当時普及し出したミシンを使って自分たちで好きな色とデザインの服を作ることが一般的でした。
2000年頃から火が付いた昭和レトロブームは、この時代の(物質的には貧しくても)文化的な豊かさへの憧れなのかもしれません。
昭和の抒情画
戦後の人々が望んでいたのは日々の華やかな暮らしぶりだけではありません。大人たちは今日の先に続く未来が素敵な世の中であることを願って止みませんでした。それには自分たちの次の時代を担う若者たちに夢や希望を抱いてもらうことが必要です。
終戦の翌年(1946年)、埼玉県蕨市では若者たちを勇気づけ励まそうと「青年祭」が開催されました。この催しは国や他県からも関心が寄せられ、現在の成人式のスタートになっています。
日本の成人式が世界の国々に比べて華やかで楽しそうな理由には、この時代の大人たちの思いが込められているからなのだと思います。
他にも戦後の近代化に向けて、それまでは不利だった女性の権利(参政権や相続権)が見直されていきます。
女性や子供の権利を侵害する「家制度」も廃止されました。
第二次世界大戦の翌年にあたる昭和21年(1946年)に創刊された雑誌「それいゆ(創刊号は「ソレイユ」)」は多くの女性たちに夢と希望を与えました。
新しい時代の女性像をイメージして「女性のくらしを新しく美しくする」をキャッチコピーにしたこの雑誌の創刊者は、戦前に竹久夢二に私淑し少女雑誌のイラストで一世を風靡した画家の中原淳一。中原の描いた少女の絵は、どこか夢現な表情で、まだ見ぬ世界への憧れと不安が混在しているかのよう。その時代の女性たちの気持ちを映しているようにも思えます。
中原淳一が雑誌「それいゆ」に込めた思い「お金をかけなくても、愉しく、美しく暮らす工夫」は、細部にまでこだわって描かれたイラストの魅力も含めて、戦後の復興を目指す人々の希望でもありました。
テレビもインターネットもない時代に雑誌は貴重な情報を発信してくれるマス・メディアであり、絵に描かれたヘアスタイルや服装は、当時ブームになっていた服飾学校に通うたくさんの女性たちが、ミシンを使って思い思いのアレンジで真似をしていました。
目に見える事実をそのまま描く「叙事」ではなく、自分の感情を表現する「抒情」という言葉は、転じて何かを観たり聴いたりした時に切なさや感動を覚えることを指します。
目に見えない気持ちを描いた絵を最初に抒情画と呼んだのは、竹久夢二に見出された画家の蕗谷虹児でした。
大正時代に女性誌に掲載されたイラストが評判になり、先輩の竹久夢二と並んで時代を代表する人気画家だった蕗谷は、本格的に絵を学ぶために名声を捨ててフランスのパリへ留学します。
既にパリで活躍していた藤田嗣二や東郷青児と親交を深めて腕を磨くと、ピカソやマティスも参加した「サロン・ドートンヌ(秋の展示会)」でも入賞を果たしましたが、家庭の事情で帰国しなくてはならなくなり、生活のために再び(不本意ながら)挿絵の仕事を始めることになります。
ところがパリで学んだ都会的な作風は、近代化の時代の波に乗り、一世を風靡することになりました。蕗谷は後に日本初のカラーアニメーション『白蛇伝』の製作にも関わり、手塚治虫や宮崎駿に大きな影響を与えることになります。
高度成長からデジタル社会へ
更に昭和30年代になると、都市部に人口が集中して、都市型経済の大衆消費時代が再び訪れます。
クリスチャン・ディオールやピエール・カルダンといったフランスのブランドが次々に日本へ進出。戦後の進駐軍によってもたらされたアメリカの文明だけではなく、最先端だったパリのファッションが輸入され、それまでの安価な既製服のイメージとは違うプレタポルテ(高級既製服)が流行。
徐々に大正時代から続いてきた「和洋折衷」も「洋風」への偏りが大きくなり始めます。
その後の日本の高度成長は世界にも類を見ないほどの勢いで、昭和の終わり頃には世界第2位の経済大国へと発展しました。
そして今、ふたたび昭和レトロへの関心が高まっています。
パソコンやインターネットが普及したデジタル化社会で、夢と希望に満ちた温かみのある昭和レトロの雰囲気は、希薄になった人間同士のつながりや美しい生活への憧憬なのかもしれません。